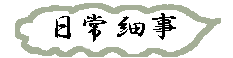
2017.8.22 職人業(技)の時代(1)
幼いころ我が家の改修工事を、朝から夕方まで飽きずに眺めていたことを思い出す。親父の仕事が最盛期の時のことで、相当な金を注ぎ込んだ工事だった。
家には多くの職人さんが入り、それぞれの仕事を手際よくこなしていた。この工事をひっくるめて大工仕事と呼ぶことにして話を進める。
大工には棟梁と呼ばれる親方がおり、その人の指示で仕事は進められる。その姿と仕事ぶりは、今手元にある江戸職人図聚(中公文庫)にある職人の姿と二重写しになる。
棟梁の姿は今でも覚えている。頭が完全に禿げ上がり見事な輝きを放っていた。家に来て庭先での最初の仕事は、鉋(かんな)を研ぐことであった。鉋の刃には三種類あるようで、荒鉋、中鉋、上鉋といって、図聚によれば「荒鉋は粗削り用、中鉋はその上をならすように平らに削る。上鉋は仕上用で、鉋屑が透けて見えるように仕上げる」
材木は削り台を設(しつら)えて作業する。三角定規の角が90度の方の形をしていて、その勾配が粗削りから仕上げになるほど緩くなっていき、仕上げの段階ではほとんど水平になっている。鉋を引く度にカールした薄紙のような鉋屑が出てくるのを、手品のような技のような思いで眺めていたものだ。
鉋のほかに墨壺と差金は大工必携の道具らしく、いつも側に置いてあった。差金(指金)というのはWikipediaによれば「 ステンレスや鋼、真鍮などの金属製で目盛りがついており、材木などの長さや直角を測ったり、勾配を出したりするのに使われる。L字型をしており、両方の辺(長手と短手(妻手))に目盛りがある。また、内側にも目盛りがある」とあり、万能物差しといったところか。墨壺は「 木でできており、壺の部分には墨を含んだ綿が入っている。糸車に巻き取られている糸をぴんと張り、糸の先についたピン(カルコ)を材木に刺す。この状態から糸をはじくと、材木上に直線を引くことができる」とあり、 木材を加工するために、印(線)をつけていく事を墨付けというそうだ。ここでは差金と墨壺はセットで仕事を果たす役割を担っている。
棟梁は仕上がった柱を手際よく計測し、墨で印をつける。そこに鑿(のみ)が登場し、切込みを入れていく。この切込みは他の木材と組み合わせるためのもので、見事にかみ合って骨組みができていく。釘など一切使わない匠の技がそこにある。ひと仕事終わると棟梁は煙管を出し、刻み煙草を詰め、火をつけるとすっと吸い込み、ふっと細い煙の筋を吐き出す。びしっと決まった一瞬だ。
次回につづく。
2017年の記事を閲覧するには日常細事のアイコンをクリックしてください。
©2013 papa's_pocket. All rights reserved.