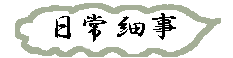
2023.12.17 諺集に見るわが人生(239)
今回は諺集(新明解故事ことわざ辞典:三省堂)「さ行」の「さから始めて、回顧していくことにする。また諺からイメージできるものについても記述する(「」の前後の句読点は省略)。
「三尺下がって師の影を踏まず(さんじゃくさがってしのかげをふまず)」弟子が師に従うときは、師を敬い礼を尽くすことを戒める言葉である。もとは仏教の作法であり、師僧に従って歩くときの心得であった。三尺は約91センチメートルで、師に随行するときは三尺離れて歩き、師の影を踏まないようにしなくてはいけない。本来は「弟子七尺去って師の影を踏まず」という言葉であった。
大谷翔平と通訳の水原一平の関係を見ると、一平は常に翔平(193㎝)後ろを守っているように見える。一平も大男(186㎝)で立派なボディーガードの役も果たしている。
「三舎を避く(さんしゃをさく)」辞退したりしりごみをすることを意味する。 相手に一目置くために謙遜することも含まれる。 三舎とは、古代中国の軍隊が1日行軍して宿舎した距離のことで、三舎を避くというのは、戦意のない態度を表す言葉。
(由来)『左伝』の中に登場する。晋の公子重耳が楚の人質となり、中原で楚の君主に会うことになった時に、「晋楚は兵を治めて中原に遇わば、君を避くること三舎せん」と言ったとされている。この言葉から、「三舎を避く」の意味が広まった。
今戦乱の中にあるロシアとウクライナ、イスラエルガザ地区の戦いなども、守る側に『三舎を避く』意志があれば100歩譲った形で戦を治めることもできるだろう。
「三十にして立つ(さんじゅうにしてたつ)」
(原文)
子曰く、
吾十有五にして学に志し、
三十にして立ち、
四十にして惑わず、
五十にして天命を知る、
六十にして耳順う、
七十にして心の欲する所に従えども矩のりを踰こえず 。
知らない人はいないほど、有名な言葉。
孔子みずからの生涯を要約した言葉だといわれている。
十五歳のとき学問で身を立てようと決心し、
三十歳でその基礎ができ、
四十歳で自分の進む方向に確信が持てるようになった。
さらに五十歳で天命を自覚し、
六十歳のときにはどんな意見にも
素直に耳を傾けられるようになり、
七十歳になると、欲望のままにふるまっても
人間の規範きはんを逸脱いつだつしないような自在の境地に達することができた。
容易ではないけれども、人生の道しるべとするだけでも、意義のある言葉だ。
次回に続く。
この記事に関するご感想などを下記メールでお寄せください。comfree@papars.net
2013年の記事を閲覧するには日常細事のアイコンをクリックしてください。
©2013 papa's_pocket. All rights reserved.