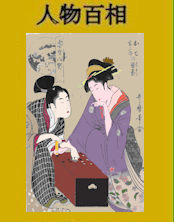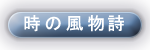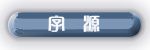八百万の神(やおよろずのかみ)
とは、神道において祀られている数多くの神々を指す言葉。
神々の数と種類の多さから「八百万の神」と呼ばれている。
このホームページは2025年8月31日付けのサーバー契約を解除し、閉館することにしました。
閉館までの間は総集編として過去のページを選択・編集して、その都度掲載します。
長らく閲覧を続けた方、一度でも来訪された方に心から感謝申し上げます。
◎URLの右端のCの頭に矢印のついた記号をクリックすると最新の情報に更新されます。
◎2024年までの記録はアイコン「過去のページ」をクリックしてご覧いただけます。
日常細事のボタンをクリックするとバックナンバーを見ることができます。日常細事はスマートフォンでもご覧になれます。
http://papars.net/2024/smartphone2024_epi/mobile2024_epi.htmlスマートフォン用「画像借景」では画像をご覧いただけます。
http://papars.net/2024/smartphone2024_epi/image2024_epi.html/English newversion here