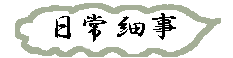
2017.7.3 禅問答(1)
今回は約束していた「年寄りの暇つぶし(3)」は内容の性質上「Writeしるす」のノートに移転することとし、昨日(2日)紹介した「Writeエッセイ」の「ことば遊び」にヒントを得て、禅問答を話題として取り上げた。
まず禅門答とは大辞林では「 禅宗の僧が悟りをひらくために行う問答。 ② 何をいっているのかわからない難解な問答。話のかみ合わない珍妙な問答」とある。これに関しては「Writeしるす」(禅に学ぶ3)でも、このような一節を見ることができる「禅僧の言葉とは常識を超えた意味のよくわからないものとして受け取られている。しかし、奇異で了解不能に見えるかと言って、彼ら禅僧の言葉が恣意的なでたらめというわけではない。一見奇異な言葉の背後にあってそれを支えているのは『語り得ないものを語る』 という真理と言語の逆説的な関係に対する彼らなりの透徹した理解なのである」という説明にあるように、禅は物事の本質、自己の本心を、直観によって明らかにすることを本分としている。
禅の修行は禅の本分に達した師に、弟子の修行僧が問い、それに師が答える。または修行僧同士がお互い問い答える。その過程で禅を会得しようと努める。それが原則だと言われている。
禅の本分は、相対的な知識を越えた絶対的な知恵の世界のことに属している。そのため、常識的な論理では理解できないことになる。
このことを捉えて、俗に訳の分からぬチンプンカンプンな問答を、禅問答のようだと風刺するようになったというのが、我々の世界の禅問答(これは「ことば遊び」で一種の洒落ととらえている)ということになる。
ところが実際は、「禅の問答は、わけの分からぬものではない。頓智や気転の類でもない。真剣に求めて、その本分に立ってみれば極めて明快である。しかも、それは常識的知性を自省させると同時に、十分納得させうるものである(東 隆真)」
次回は禅問答の具体例を上げて、その内容を見ることとする。
2017.7.6 禅問答(2)
禅問答というのは、特別の宗派には見られない特色の一つと言ってもいいだろう。禅には経も文字さえ不用(不立文字という)であるとされている。
そういう所から悟りを得た師と修行僧等の間での問答が学ぶのに欠かせない。これは最初に記した通りだが、こうした形はギリシャ哲学やキリスト教、仏教でも対話形式による伝承が行われており、これらは知的かつ論理的内容を持っている。
これに対し禅問答は論理的でも説明的でも解釈的でもない。言わば「場当たり」的ものである。一問一答で終わり知的でなく発展性もない。
鈴木大拙氏はこの禅問答について「禅問答は剣客の立ち合いになぞらえられる。一方の大刀が動くかと思うと、相手は倒れている。巌流島の武蔵と小次郎の対決のようなものである。両刃鉾崎(りょうじんほこさき)を交えて避くることをもちいずともいう」と表現している。
禅問答の一例を一休噺の「屏風(びょうぶ)の虎退治」から引いてみる(石井清純『禅問答入門』)。
それは、将軍足利義持に「屏風の虎が夜な夜な出歩いて悪さをする。退治してくれないか」と請われた一休が「分かりました。私は前で待ち構えていますから、将軍様、虎を追い出してください。出てきたところを退治しましょう」と言って義持の無理難題を退けたという噺である。
この逸話は、達磨とその弟子慧可(えか)の問答で明らかにした「心の不安」というものは「じつは確固たる実体のないものであり、それに対する恐れや拘りさえ捨て去れば、自然に解消されるものであることを示した」という。こうしたやり取りが禅問答の主題となっている。
多くの禅問答の弟子に対する師の答えは(鈴木)「なんともわからぬ一種のすっぽかしのような、問者を愚弄したようにも感じられる。もし、問者に師に対する絶対的信頼がないと、相手が一生懸命な態度にあるにも関わらず、まるで答者は木で鼻を括るような風に見える。場合によっては一喝を浴びせられたリ、一棒をくらわされたりすると問者は憤然とすることだろう。ところが答者は問者を超越した次元から答えを発する。すなわち、禅の答は、いつも問者と違った立場から出るものと考えておかねばならない]
最後の一例はその最たるものである。
投子和尚、因み(ちなみ)に僧問う「如何なるか是れ道」。和尚曰く「道」。「如何なるか是れ仏」。和尚曰く「仏」。
答えは問いを発する者の中にあり、それに目覚めるというところにあるのだろう。
2017.7.10 男・女?!(1)
人間は二種類、男か女しかいない。生まれる時どちらかの性を持って誕生する。現在、私には3人の姉と2人の妹がいる。多くの女性の中で育った。さぞ羨ましいことだと思う人もいるかも知れないが、姉や妹は性別を越えた特別な存在としか言えない。
自分のことはさておき、男と女の関係といえば、磁石の両極のようなもので、お互いに惹かれ合うようになっているらしい。高校生ぐらいまでは絶対に女性の方が分別もあり、大人である。その食い違いが異性を意識することになる要因なのだろう。男の場合これは性の本能のようなもので、大概の場合女性の発するフェロモンにコロッと参ってしまう。遅かれ早かれ恋に陥ることになる。惚れてしまえばアバタもエクボの譬えにあるように、つがいの鳥のように結ばれることになる。これは男女の通過儀礼のようなものなのかも知れない。
ところが、恋などは一時の夢のようなもので、いつかは冷めるものである。その後は幾通りもの道が待ち受けている。磁石のように引き合っていたものが、裏返しの反発に転じることだって決して珍しい現象ではない。物理の法則に習えば当たり前なことなのだ。
その辺のところを冷静に分析して見ることにしよう。その分岐点は愛情の存在にある。そこまで相互が認め合える存在になるには1年や2年の年月ではとても無理な話なのである。母親が一人息子に注ぐ愛情などは特別で無条件なところがある。そんな愛情は自分の分身だからであって、元々といえば他人の二人がそんなに強い愛情で結ばれるということはまずないだろう。
そこまでの愛情を期待するのでなく、切れず離れずに関係が持続する程度の愛情を認め合うことができれば、この結婚は大成功の部類に入る。今回はここまで、これからの話は少し込み入った展開を見せることになる。(続く)
2017.7.13 男・女?!(2)
男と女が相互に惹かれて結ばれるメカニズムは、今までの考察で分かった。そこまでの道筋は成り行き次第ということになる。
これからは比喩や諺などを使いながら夫婦の在り方を見ていくことしよう。古来より男は結婚を後悔する言葉に埋もれている。
結婚してみて、お互いに「よい結婚はあるけれども楽しい結婚はめったにない。ラ・ロシュフコー」とうことに直ぐ気がつく。
まず最初の危機は妊娠である。男にとってこの事実は恋の終りを意味する。ここで男と女の性の違いが明確に出る。女はお腹の子によって恋とは違う「愛情」を知る。ところが男には、家族ができるという実感がない。妻の目は自分には向いておらず、わが子に向いている。若い夫にとって、ここ一番の辛抱時を迎えるのだが、時代は男の家長意識を希薄にしている。 家とか家族という昔は当然のように受け入れられた慣習は過去のものとなっている。そうした社会の変化が男の意識を変え、次なるたとえ話「結婚とはセルフサービスの食事のようなものだ。 自分の欲しい料理を選んだ後で、隣りの人たちのお皿の中身を見る。 そして、どうして自分は彼らと同じ物を選ばなかったのだろうと自問するのである。J・ドラークル」という状況を生み出すことになる。この心の隙間に浮気心が生じる。だがしかし、それには当事者である男に、甲斐性と金銭力そして魅力が備わっていなければ、解消できる話ではない。
たとえダメ男でも女は男の心変わりに敏感に気づく。その頃には相互の会話も減り、コミュニケーションも取りにくい状況になっている。この冷戦は、絶対的に女性優位の立場から始まる。1対1の対決ではなく、ここでは1対2(女性にはお腹に強い味方が付いている)の争いで、男に勝ち目はない。一番の解決策は男がまず白旗を上げるべきで、それが最良の策である。そこで男は「できるだけ早く結婚することは女のビジネスであり、できるだけ結婚しないでいることは男のビジネスである(ジョージ・バーナード・ショー) 」という後悔の念にかられることになる。
そして事実上の勝利者の妻は「亭主元気で留守が良い」という形を作り出し、昔とはすっかり様変わりした「亭主関白」ならぬ「鬼嫁」として家を仕切ることになる。
ここまでが最初の危機に関する私の一般的考察である。次回はもう少し違った状況から男女関係を見てみたい。
2017.7.16 男・女?!(3)
私が見るところでは、結婚して子どもが出来ない夫婦はなぜかオシドリ夫婦が多い。前回の観察で、必ずしも「子は鎹」になり得ないことは分かった。子どもが出来ないということと、作らないということは別物である。巷間よく耳にした DINKs(ディンクス)というという略語 があるが、このケースは共働きで子供を意識的に作らない、持たない夫婦、またその生活観のことを指すもので、そういう関係がいつまで続くのかは予測できないし、二人がどのような愛情関係にあるのかも分からない。
私が知っている子どものいない夫婦は、欲しくても出来ない体質的制約がある夫婦だ。こういった夫婦は添い遂げる。いつも二人だから、いつも一緒に行動を共にし、旅行したり食事に出かける。一緒にいる時間が多ければコミュニケーションもよく取れる。お互いに秘密にしていることがあるかどうかは知る由もないが、見た目には仲が良く見える。
かつての家社会においては、家の跡継ぎという問題があった。貝原益軒も「 『女大学』で「嫁して三年子なきは去る」という言葉を残している。 家の存続のため、無理をしてでも子供が生めない女性を離縁させた」という記述であるが、家制度が崩壊した現在では、特定の家系を除いては、そうした理由で別れることはまずない。
二人生活が長く続くと、恋の延長で特殊な愛情が芽生えるのかもしれない。よく離婚の原因に上げられるのが「性格の不一致」だが、これこそ取ってつけたような理由で、多くは不倫かDVが原因に違いない。こうした関係は共同生活すれば、比較的早くに兆候が出るもので、その時点で修復不可能と考えていいだろう。
逆説的に長く連れ添う夫婦はお互いを思いやるから持続するのである。
私は教会で結婚式を挙げたが、その時の宣誓文は「わたしが自分の全財産を人に施しても、また、自分のからだを焼かれるために渡しても、もし愛がなければ、一切は無益である。「コリント人への第一の手紙-13章」だったと覚えているが、いまだに夫婦の愛情とはどういうものなかはよく分からない。あの誓いも遠い昔の話となってしまった。
2017.7.20 宿命
人は生まれることと死ぬことは自分では選択できない。それが宿命だ。最近長寿で活躍し文化勲章も九十歳を超えて受賞した日野原重明聖路加病院名誉院長が、105歳で死去との報道を聞いた。103歳まで現役で活躍していたという、まさに人生現役を実践した偉人である。 90歳で出版した『生きかた上手』はミリオンセラーとなったように、超高齢者にとって生きる支えにもなっていた人を失ったことは残念だ。
同世代の加山雄三若大将も80歳を過ぎて現役バリバリである。私には怪物としか映らない。彼も又三浦雄一郎同様100歳現役もしくは生涯現役を貫くことだろう。
このように周りを見渡せば、多くの高齢者 (内閣府の調査で、70歳以上あるいは75歳以上を高齢者と考える意見が多い結果になっていることなどを踏まえ、「65~74歳までを"准高齢者"、75~89歳までを"高齢者"、90歳以上を"超高齢者"」として区分することの提言している)が、現役で活躍していることが珍しくない時代に入っている。わが稿でも 『年寄りの暇つぶし』でも紹介したばかりだ。
振り返ってわが身を見るに、数えで傘寿を迎えているが、どうも危なっかしい状況にある。ここ数週間体調が崩れ、おなかの具合も悪く、体重も急速に減っている。それは食欲がないからで当然なのだが、1週間ほど前から帯状疱疹が背中から脇の下、腹部へと広がっている。体の抵抗力が弱まって、子どもの頃の水疱瘡のウィルスが息を吹き返したせいだそうで、免疫の錠剤を6日間飲み続けた。この薬が強烈で一日中倦怠感が抜けない。弁解がましいが、ここのところ1日1回のホームページの更新がやっとの状況で、意地で書いて(描いて)いるといった塩梅だ。
持病の腰痛は歩行もつらい状態だし、これでは「泣き面に蜂」というやつで、人生ここまでかといった弱気も頭を持ち上げる。人の生死は宿命だから成り行きに任せるしかないが、この一山(実は二山目)を越えれば、弱気の虫も飛んで行ってしまうだろうが、その時がくるまで、「痛いの痛いの飛んでけ」と呟き続けているところだ。
ウ